浅水域における貧酸素水層の形成と解消:渦相関法による酸素フラックスの定量化
2024年10月9日
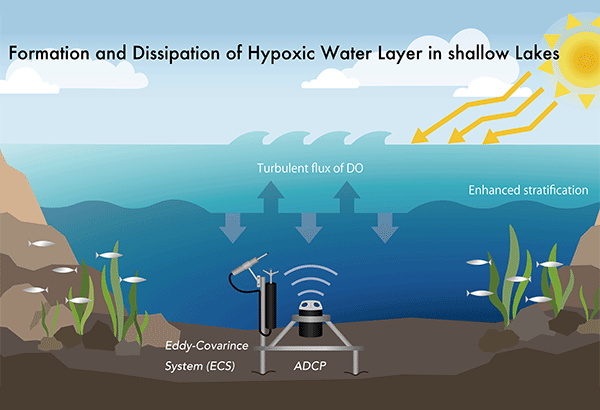
研究成果
発表者
川口 悠介 海洋物理学部門 助教
増永 英治 茨城大学 地球・地域環境共創機構 講師
北村 立実 茨城県霞ケ浦環境科学センター 主任研究員
大内 孝雄 茨城県霞ケ浦環境科学センター 主任
孫 恩愛 海洋物理学部門 特任研究員
成果概要
東京大学大気海洋研究所、茨城大学、茨城県霞ケ浦環境科学センターの研究グループは、茨城県・霞ヶ浦の北浦湖において、夏季に発達する貧酸素水層の調査を実施し、湖水温上昇に伴う貧酸素水層(注1)の発達・解消プロセスにおける乱流混合(注2)による酸素フラックスの実態の把握と定量化に初めて成功した。渦相関法(注3)による酸素フラックス計測の技術が広まることで、湖沼だけでなく、内湾など流れが弱く水が淀みやすい浅海域における漁業資源の管理や環境保全への貢献が期待される。
発表内容
研究背景
地球温暖化やエルニーニョ現象の影響で、近年は日本各地で夏季の記録的猛暑が観測されている。湖沼や内湾の浅海域など、水の循環が弱く淀みやすい水域では、高気温や強い日射によって表層水温が上昇する(図1)。このような時期は、上層の水の密度が下層に比べて軽くなることで密度躍層(注4)が発達し、上層と下層の間の水塊および物質交換が妨げられる。上下層の水の入れ替わりが停止することで、下層の水に溶けた酸素(溶存酸素)の濃度は、水棲生物の呼吸やバクテリアの分解の作用によって消費され、貧酸素(酸素濃度が2-3mg/L以下)もしくは無酸素(0.5mg/L以下)の状態に陥る。一旦貧酸素の状態に陥ると、そこをすみかとする魚類や甲殻類など酸素を必要とする生き物の一部が窒息死し、地域の生態系に深刻な影響が及ぶことが知られている。また、溶存酸素が枯渇した状態において、湖底の泥質から金属物質(鉄、亜鉛、鉛など)が通常よりも多量に溶出するという研究結果もある。そのため、貧酸素水層の形成と解消のサイクルおよびその物理メカニズムを明らかにすることは、漁業・水産資源および環境保全の観点から重要な喫緊の課題と言える。
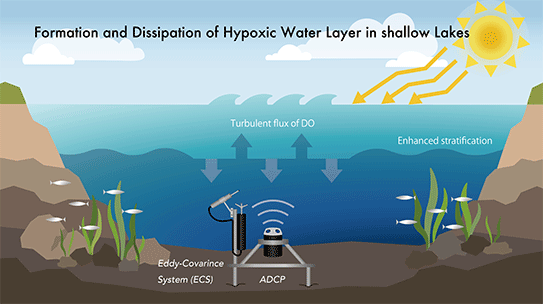
図1:湖沼における貧酸素水層の形成メカニズムと渦相関フラックス計を用いた乱流酸素フラックスの観測の模式図
水の流れが弱い沼や浅い湖では、下層での貧酸素水層の形成と解消のサイクルは、上層からの酸素供給と現場での酸素消費の過不足によって決まる。ここで、上層からの酸素供給とは、表層の風応力などによって水が混合され、表層付近の高酸素濃度の水が下層に流入することを意味する(図1)。上層から下向きの乱流酸素輸送(以下、フラックス)があることで、下層の貧酸素状態は徐々に解消されていくと考えられている。もしくは、植物プランクトンの光合成によって水中の溶存酸素濃度が回復する。先行研究の多くは、水中の溶存酸素濃度の変化と水上の風速や放射量との相関関係などから、経験的・演繹的な手法で溶存酸素フラックスを推定してきた。しかしながら、これらは乱流による溶存酸素の動きを直接捉えているわけではないため、酸素が輸送される物理プロセスを深く追求することは得意としない。
研究内容
そこで本研究は、渦相関法という観測手法を用いて、乱流による溶存酸素フラックスを直接計測する試みを行った(図1)。渦相関法は、乱流による水の動きと酸素濃度の変動成分とを同時に計測し、クロススペクトルを用いて処理することで2変数間のフラックス値を得る手法である。酸素フラックス以外にも、熱や運動量(例えば、東西成分 vs 鉛直成分)に関する乱流フラックスも計測が可能である。この手法を用いることで、変数同士の相関(コヒーレンス)や位相差に関する統計学的な情報を引き出すことが可能となる。
本研究では、この渦相関フラックス計を霞ヶ浦の北浦湖の湖底付近に設置し、2022年5月から7月にかけて約3か月間の係留調査を行った。渦相関観測と並行して、各層での流れの向きと速さを取得する多層型ドップラー流向流速計(ADCP)を用いた観測も行った。さらに、湖水の水温、成層、酸素の鉛直構造を知るために、観測地点からほど近い釜谷ステーションで取得された多項目水質計のデータも解析に使用した。
今回の観測から、6月中旬から徐々に高気温が観測され始め、高気温と風のない穏やかな気候が続くことで、湖の水温が次第に上昇するとともに、中層付近に水温による強い密度成層が発達する様子が観測された(図2b)。中層の温度躍層の下では酸素量濃度が2 mg/Lを下回る貧酸素水層の形成が確認された(図2e)。渦相関計の計測から、水温躍層が卓越し、上下層間の酸素濃度の差が最大限に拡大した頃合いに、上層から下層への乱流による溶存酸素フラックスが観測された(図3c)。これは、溶存酸素濃度の急峻な鉛直勾配を是正し、底層の酸素枯渇状態を回復するために乱流による酸素輸送プロセスが機能したものと解釈される。
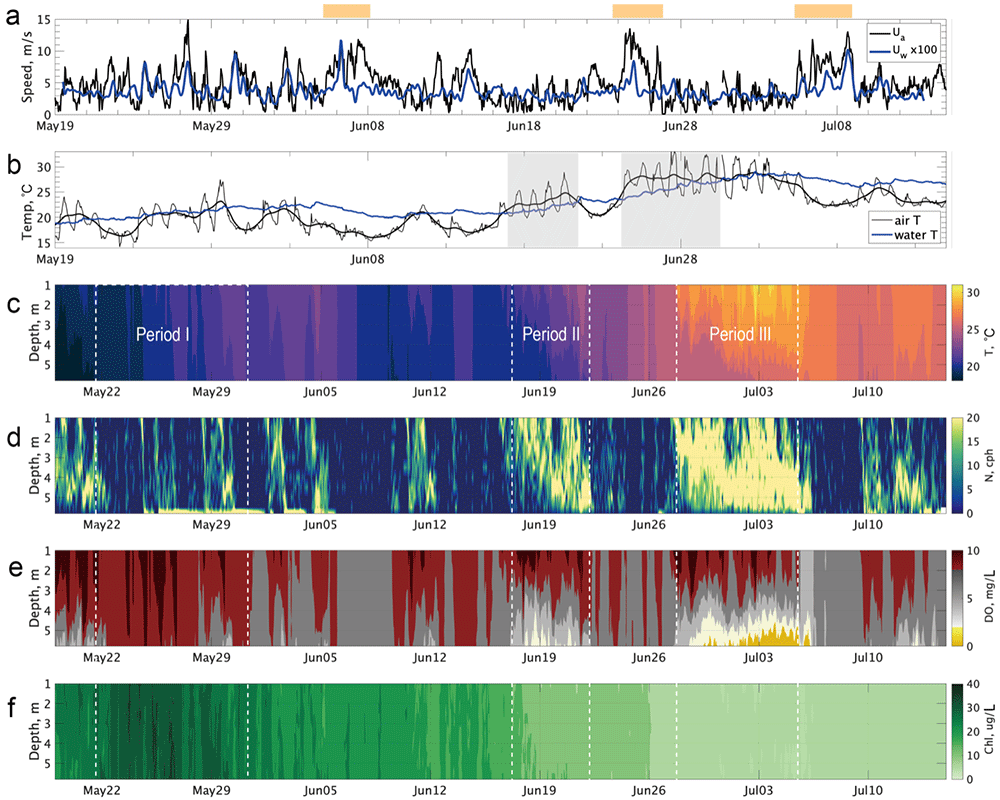
図2:霞ヶ浦・北浦湖で観測された(a)風速&流速、(b)気温&水温の時系列、(c)水温、(d)成層、(e)溶存酸素、(f)クロロフィルの鉛直-時間断面
(a)にて図上部の橙色は強風イベントを、(b)の灰色帯は水温が気温を上回る逆転イベントを示す。(c-f)のPeriod Iは成層が弱く、Period II,IIIは成層が発達した時期を示す。
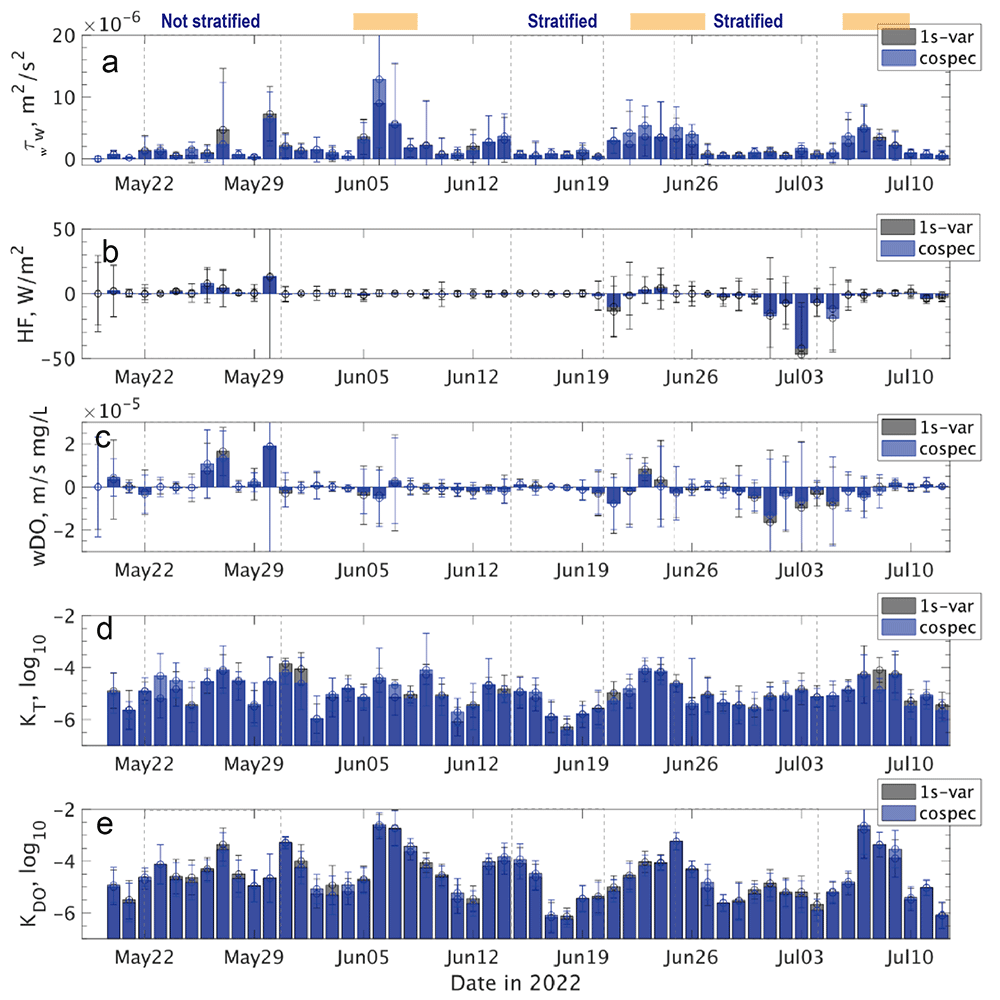
図3:渦相関法で得られた乱流変数の時系列:(a)摩擦速度、(b)熱フラックス、(c)酸素フラックス、(d)水温の拡散係数、(e)溶存酸素の拡散係数
(b)(c)は正が上向き、負が下向きを示す。
社会的意義・今後の展望
渦相関法による酸素フラックスの計測は、湖沼以外にも、流れが弱い内湾や浅めの沿岸域の下層に形成される貧酸素の問題に応用することで、溶存酸素のバランスや変動成分についてより正確に見積もることが可能となる。エコシステムや漁業資源、環境保全の観点からも今後、渦相関法によるフラックス定量化の技術の有効性が期待される。
最後に、本研究で用いた渦相関フラックス計は、北極海の海氷直下における海洋中の熱フラックスを計測するために開発された技術である(下記のプレスリリース)。溶存酸素だけでなく、流体の乱流混合によって運ばれる任意のスカラー量への応用が可能である。本技術に適用可能なセンサーを用いて、学際的な研究の発展に力を入れていく予定である。
プレスリリース:±0.01℃精度の海水温の揺れが物語る北極海の異変―夏と冬とで異なる海氷の動きやすさと海氷分布の変化―(2024年7月8日)
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2024/20240708.html![]()
発表雑誌
雑誌名:Limnology(2024年9月27日)
論文タイトル:Eddy-covariance measurements of turbulent fluxes across the oxygen-depleted benthic layer in a shallow stratified lake
著者:Yusuke Kawaguchi*, Eiji Masunaga, Takao Ouchi, Tatsumi Kitamura, Eun Yae Son
DOI番号:https://doi.org/10.1007/s10201-024-00763-8![]()
アブストラクトURL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10201-024-00763-8![]()
用語解説
- (注1) 貧酸素水層
- 水中の溶存酸素濃度が2 mg/Lを下回る層。呼吸を必要とする水生生物(魚類や甲殻類)に健康被害をもたらし、湖底の堆積物から栄養塩や有害金属が溶出する原因となる。
- (注2) 乱流混合
- 流体中で発生する無秩序で複雑な運動により、物質やエネルギーが効率的に混合される現象。湖沼の物質輸送、エネルギー交換において重要な役割を果たす。
- (注3) 渦相関法
- 流体の運動と物質やエネルギーの輸送量を高精度に測定する手法。乱流フラックスを捉え、気候変動や生態系研究で重要な役割を果たす。
- (注4) 密度躍層
- 湖沼において、水温の急激な変化により形成される層で、表層と深層の間に位置する。上下の水の混合を制限し、酸素や栄養塩の分布に影響を与える。
問い合わせ先
川口 悠介
海洋物理学部門 助教
ykawaguchi◎aori.u-tokyo.ac.jp ※「◎」は「@」に変換してください
![]()
![]()

 教職員募集
教職員募集 所内専用
所内専用
