環境DNAを使用した海洋表層の高解像度魚類モニタリングの可能性
2025年9月16日

研究成果
発表者
Ahmed Sk Istiaque 海洋生物資源部門 大学院農学生命科学研究科 博士課程
伊藤進一 海洋生物資源部門 教授
成果概要
近年、魚類から水中に放出されたDNA(環境DNA)を用いた魚類分布調査が開始されました。一方で、フェリー等の協力船の船底汲上水による水温モニタリング等が実施されていますが、配管中の金属等による環境DNAへの影響は未検証でした。東京大学大気海洋研究所のAhmed Sk Istiaque大学院生と伊藤進一教授らの研究グループは、共同利用学術研究船で船底汲上水、バケツ採水、ニスキン採水器から環境DNAを採集し、魚類群集構造や多様性が概ね一致することを示しました。本成果は、船舶停止を必要としない船底汲上水による連続環境DNA採集によって広域かつ高解像度な環境DNAモニタリングが可能なことを示すものです。
発表内容
研究背景
魚類から水中に放出されたDNA(環境DNA)を用いた魚類分布モニタリングは、生物を捕獲する必要がない非侵襲的な調査方法として注目されています。特に、環境DNAのメタバーコーディング解析は、存在する魚類を網羅的に調べることができ、海洋生物多様性を把握する上で有効です。これまで、表層の魚類環境DNAを採集する方法としては、ロープにバケツを括り付けたバケツ採水やニスキン採水器という採水器を用いた方法が広く用いられてきましたが、いずれも船舶を停止させる必要があり、時間的制約を伴います。
一方で、船底から海水を汲み上げる船底汲上水は、船舶を停止することなく採水が可能であり、研究船だけではなく、フェリーや貨物船などの協力船においても、水温や二酸化炭素分圧などのモニタリングを行う自動観測装置が稼働しています。これらの協力船による海洋モニタリングは、大陸間の外航航路でも実施されており、高解像度・高頻度なモニタリングを可能としています。しかしながら、船底汲上水では配管や配管の腐食防止材などの金属の影響や、配管内の生物付着に付随するバクテリアの影響など環境DNAを用いた魚類検出に影響を与えるリスクが指摘されており、船底汲上水による環境DNAモニタリングの有効性の検証が必要とされていました。
研究内容
研究チームは、西部北太平洋における9回の共同利用学術研究船による航海の83地点において、船底汲上水(水深3~5m)、バケツ採水(水深0m)、ニスキン採水器採水(水深5または10m)の3種類の採水試料から魚類環境DNAを採集し、比較しました(図1:採水地点)。その結果、各手法で324分類群以上、合計464分類群が検出されました。全観測点のデータを用いた魚類の多様性は、3種類の方法で概ね一致する傾向を示しました(図2)。
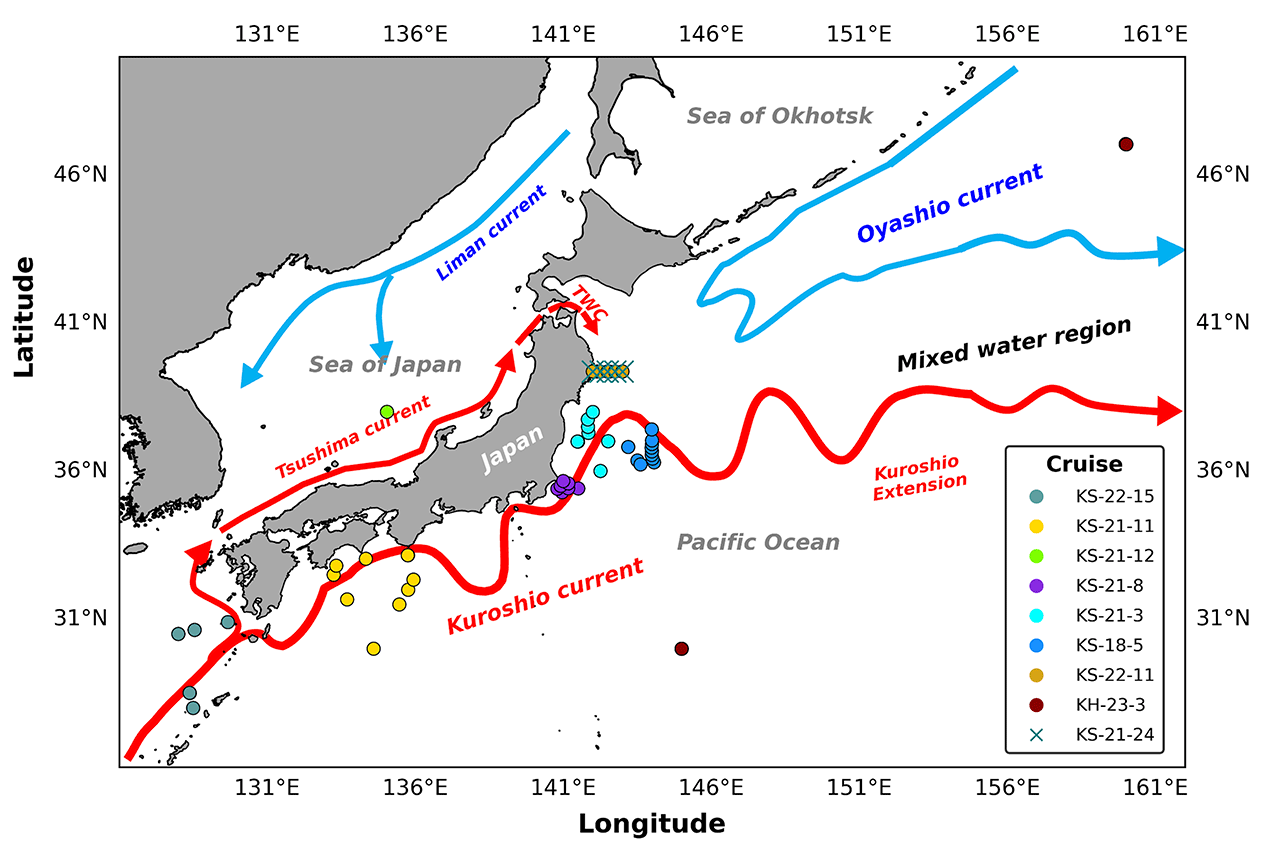
図1. 調査航海の採水地点と主要な海流(黒潮・親潮・対馬海流など)の位置関係(Ahmed et al., 2025より)

図2. 3種類の採水法で検出された魚類多様性と外挿曲線
多様度指数はq0(種数)、q1(シャノン)、q2(逆シンプソン)。色は手法を示し、青:バケツ、ピンク:船底汲上水、緑:ニスキン採水器(Ahmed et al., 2025より)。
しかし、北西太平洋では海域間の環境が大きく異なるため、環境に依存した多様性の変化が3種類の方法の比較に影響している可能性があります。そのため、群集組成(種毎の在・不在)に基づいたクラスター解析を実施したところ、8つの特徴的な群集組成に分類され、ほとんどの場合、同じクラスター内に同じ観測点で3種類の方法によって検出された群集組成が含まれることが示されました(図3)。各群集組成は、水温などの環境要因や季節に依存して現れますが、同じ地点、領域で3種類の方法で検出される群集組成を比較すると類似していることがわかりました。一方で、バケツ採水では一部の地点で多様性が過大評価されるリスクがあることが示されました。

図3.3種類の採水法の魚類群集構造の非尺度型多次元構成法による分布
楕円形は8つのクラスターを示し、印は各クラスターに含まれる採水サンプルを示す。色は3種類の採水法を示し、青:バケツ、ピンク:船体汲上水、緑:ニスキン採水器。矢印及び黒字は環境要因(温度・塩分・クロロフィルa)および季節の影響の方向を示す(Ahmed et al., 2025より)。
社会的意義・今後の展望
本研究は、船底汲上水による環境DNA採水法が他の良く用いられる採水方法と同等の魚類群集組成および多様性を検出できることを支持するものです。船底汲上水を用いたモニタリングは、船舶を停止させる必要がなく、自動観測装置による連続観測が可能なため、広域的な高頻度かつ高解像度な魚類多様性の把握を可能とします。今後、表層魚類多様性の時空間的な観測が地球規模で拡大し、気候変動に対する表層魚類の応答特性が解明され、持続的な漁業資源管理に資することを期待します。
発表雑誌
雑誌名:Journal of Oceanography (2025年8月1日)
論文タイトル:Patterns in marine surface fish biodiversity and community composition detected by different eDNA metabarcoding sampling methods
著者:Ahmed S. I.*, Z. Yu, T. Higuchi, J. Inoue, M. K. Wong, X. Wang, Y. Lin, S. Itoh, K. Komatsu, E. Tsutsumi, H. Fukuda, Susumu Hyodo, J. Morrongiello, E. M. Bendif, S. Ito*
DOI番号:10.1007/s10872-025-00771-x
アブストラクトURL:https://doi.org/10.1007/s10872-025-00771-x![]()
問い合わせ先
伊藤進一(いとう しんいち)
海洋生物資源部門 教授
goito◎aori.u-tokyo.ac.jp
※アドレスの「◎」は「@」に変換してください
![]()
![]()

 教職員募集
教職員募集 所内専用
所内専用
