バイオインフォマティクスを用いたサンゴ骨格マグネシウムの輸送経路に関する推定
2025年4月21日
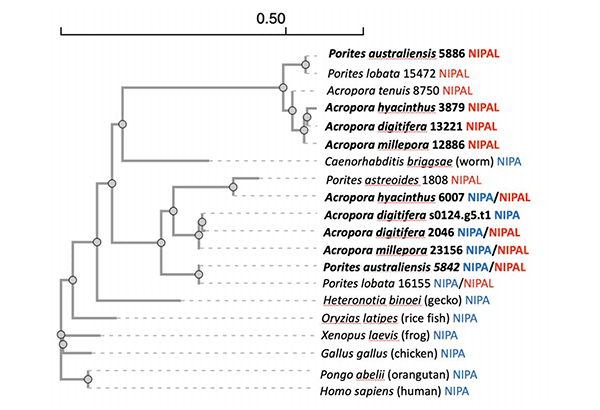
発表者
ベル智子 Newman University
Division of Science and Mathematics Assistant Professor
井口 亮 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 主任研究員
大野良和 北里大学海洋生命科学部 特任助教
酒井一彦 琉球大学 熱帯生物圏研究センター 名誉教授
横山祐典 海洋底科学部門 / 先端分析研究推進室 教授 / 室長
成果概要
地球の過去の環境を正確に復元することが求められる古気候学では、プロキシと呼ばれる元素分析が必要であり、どの元素を選定するかが非常に重要と考えられています。現在、プロキシの選定手法は一貫した理論を用いた選定というよりは、経験的なデータに基づいて選択しているのが現状です。例えば、サンゴ骨格中のストロンチウムは生物学的効果が少なく環境復元に適していると多くのデータが報告されており、マグネシウムに関しては生物学的効果が大きく、海水温などの環境復元には不向きであると報告されていました。私たちの研究では、このように元素によって、大きな差が出てしまうのは何故だろうという疑問にバイオインフォマティクスの手法を用いて取り組む研究を行いました。この新しいアプローチは生物学的効果の影響を強くすると考えられる元素を予測するだけでなく、なぜ影響が出ているのかという説明をすることを可能にすると考えられます。今回の研究はサンゴだけでなく、炭酸カルシウムを形成する、あらゆる生物を用いた環境復元の研究に貢献することが期待されます。
発表内容
【研究の背景】
地球の過去の環境を正確に復元することが求められる古気候学では、プロキシと呼ばれる元素分析が必要であり、サンゴ骨格を用いた元素分析では、ストロンチウムが特に有効であると考えられています。ストロンチウムとは対照的に、マグネシウムはサンゴの個体差が大きいと考えられ、海水温などの古環境復元に不向きな元素とされています。先行研究では、このような元素による差が出てしまう原因を一貫した理論で説明することが難しく、生物学的要因という一括りでの説明にとどまっていました。本研究では、この疑問にバイオインフォマティクスの手法を用いて取り組む研究を行いました。
【研究内容】
私たちは、マグネシウムを海水から能動的に輸送していると考えられるサンゴのマグネシウムトランスポータが数百万年かけて進化している証拠を報告しました。更新世(注1)に出現したサンゴは、鮮新世(注2)に出現したサンゴに比べて、ヒトのような脊椎動物と高い類似性を示すマグネシウムトランスポータを有することがわかりました。この結果は、サンゴがマグネシウムを海水から輸送するシステムは生物学的進化の対象であり、海水温などの無機的な環境要因の復元に不向きであるという説明をすることができます。
【社会的意義】
私たちは、このような元素の輸送に関する進化の証拠は、生物学的要因の強さを評価する基準となるということを提案します。このアプローチはプロキシの選定に貢献するだけでなく、何故、プロキシとして選定された元素が古環境復元において有効であるかという説明をすることが可能となり、プロキシの信頼性を高め、正確な環境復元に貢献することが可能となります。また、このアプローチはサンゴだけでなく炭酸カルシウムを形成する、あらゆる生物を用いた環境復元の研究に利用されることが期待されます。
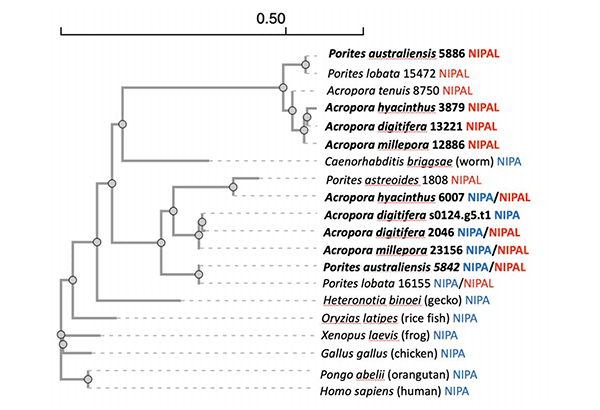
図1 マグネシウムトランスポータの系統樹。太字で書かれているサンゴ種は更新世に出現したサンゴで鮮新世のサンゴより、脊椎動物のマグネシウムトランスポータとの類似性が高い。
発表雑誌
雑誌名:Royal Society Open Science(2025年1月22日)
論文タイトル:Bioinformatic approach to explain how Mg from seawater may be incorporated into coral skeletons
著者:Tomoko Bell*, Akira Iguchi, Yoshikazu Ohno, Kazuhiko Sakai, Yusuke Yokoyama
DOI番号:10.1098/rsos.232011
URL:https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232011![]()
研究助成
Collaborative Research at the Tropical Biosphere Research Center, University of the Ryukyus
用語解説
- 注1 更新世
- 第四紀と呼ばれる地質時代に含まれ、人類が進化ー拡散した時期と重なる。約260万年前から1万1700年前にあたり、チバニアンも更新世の一部である。
- 注2 鮮新世
- およそ533万2千年前から258万8千年前を指し、新第三紀の後半の時代にあたる。哺乳類が分化、大型化、特殊化した。(産業技術総合研究所 地質調査総合センターHP
 )
)
問い合わせ先
ベル智子(べる ともこ)
Newman University Division of Science and Mathematics
Assistant Professor
bellt◎newmanu.edu
横山祐典(よこやま ゆうすけ)
東京大学大気海洋研究所 海洋底科学部門 / 先端分析研究推進室
教授 / 室長
yokoyama◎aori.u-tokyo.ac.jp
※アドレスの「◎」は「@」に変換してください
![]()
![]()

 教職員募集
教職員募集 所内専用
所内専用
