北太平洋の亜鉛とケイ素の乖離を海洋物質循環モデルで再現
2024年10月22日
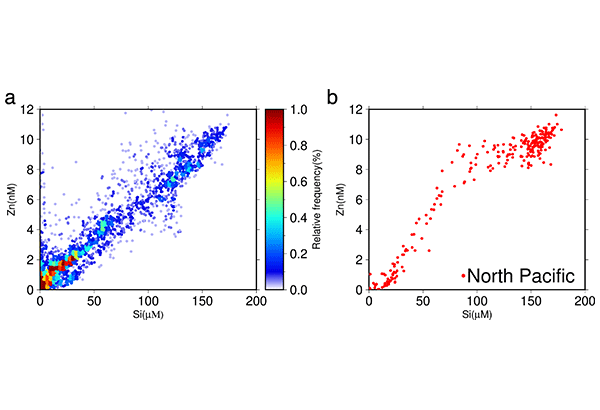
研究成果
発表者
| 杉野 公則 | 気候モデリング研究部門 博士課程 (大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻) |
| 岡 顕 | 気候モデリング研究部門 准教授 |
研究概要
海洋中の亜鉛の分布はケイ素に類似しているものの、近年の観測結果から、北太平洋では亜鉛の分布がケイ素の分布から乖離していることが指摘されていました。大気海洋研究所の杉野公則大学院生と岡顕准教授の研究グループは、この乖離の原因について、ケイ素と亜鉛の全球分布を再現するための海洋物質循環モデルを用いたさまざまな数値実験を実施することで検証しました。この結果、北太平洋の陸棚域からの亜鉛の供給を考慮したモデルで、北太平洋における亜鉛とケイ素の乖離の再現に成功しました。本研究は、海洋中の亜鉛の北太平洋を含む全球的な分布の再現に成功するとともに、海洋物質循環における北太平洋大陸棚の重要な役割を示唆した点で大きな意義を持ちます。
発表内容
研究背景
亜鉛や鉄は海洋中の微量栄養塩元素(注1)の一つです。微量元素は、海水中に存在する量がごくわずかなため、濃度の測定が困難であり、従来その観測値は限られた観測地点においてのみ判明していました。しかし、GEOTRACES計画(注2)により、近年、全球的な微量元素の分布が徐々に明らかにされてきており、海洋中の微量元素分布を決めるプロセスに関する研究も進んでいます。亜鉛は細胞体内に取り込まれ、有機物粒子として海洋内部へと沈降していきます。したがって、本来的には同じプロセスで海洋内部を循環する主要栄養塩のリンとの連動性が高いものの、実際の海洋内部の亜鉛の分布はリンよりも、珪藻中の殻に取り込まれるケイ素に類似しています(図1a)。これは、南大洋で優占して存在する珪藻が亜鉛を効率的に取り込むことで、南大洋表層ではリンよりもケイ素と似た濃度分布を作り出し、ケイ素と亜鉛が枯渇した特徴をもつ南大洋表層水が沈降して各大洋へと広がっていくためとされています。しかし近年の観測結果から、北太平洋では亜鉛の鉛直分布がケイ素の分布から乖離していることが指摘され、この乖離をもたらす機構についての研究が必要となっていました(図1b)。
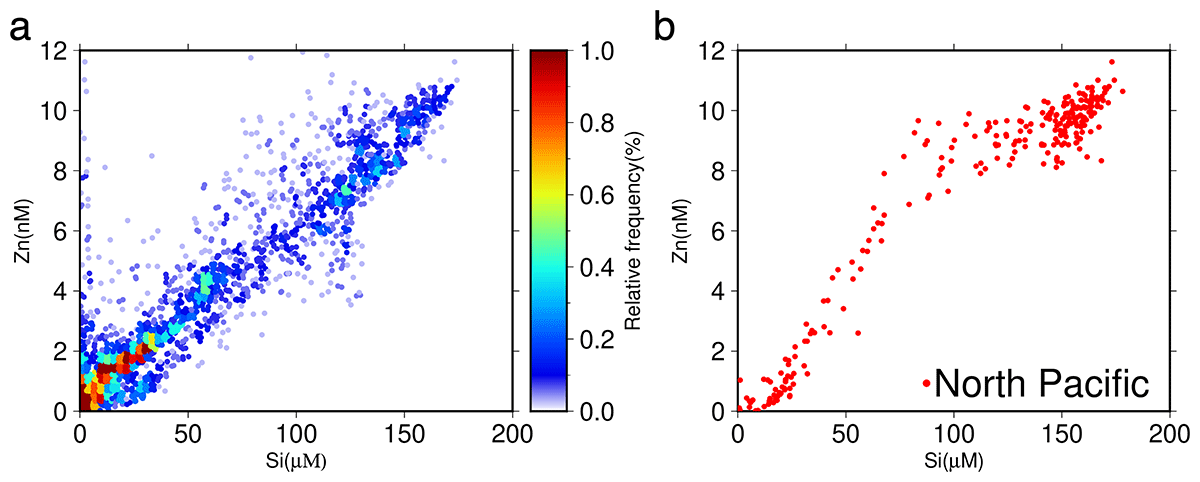
図1.GEOTRACESデータの珪素(横軸)と亜鉛(縦軸)をプロットした散布図
(a) 全球データの散布図。色付けはプロットデータの頻度を表す。(b) 北太平洋におけるデータ(GP02セクション; 図3(a)参照)の散布図。
研究内容
本研究では、北太平洋における亜鉛とケイ素の乖離の原因について、ケイ素と亜鉛の全球分布を再現するための海洋物質循環モデルを用いたさまざまな数値実験を実施することで検証しました。この結果、陸棚からの溶出過程を入れない従来のモデルでは、現実的な値を超える極端なパラメータ設定を用いた実験も行うなどして、亜鉛とケイ素の乖離の再現を試みたものの、いずれの結果もその乖離を再現することができませんでした(図2)。従来のモデルではパラメータをどのように変更しても北太平洋の亜鉛観測値を再現できない一方、北太平洋の陸棚域であるオホーツク海およびベーリング海からの亜鉛供給を新しく考慮したモデルでは、北太平洋における亜鉛とケイ素の乖離を再現できると同時に、他の海域における亜鉛とケイ素の分布の類似は崩さずに再現できることが確認されました(図3)。これは北太平洋における亜鉛とケイ素の乖離の原因として海洋から北太平洋大陸棚からの亜鉛供給の存在を支持する結果でした。
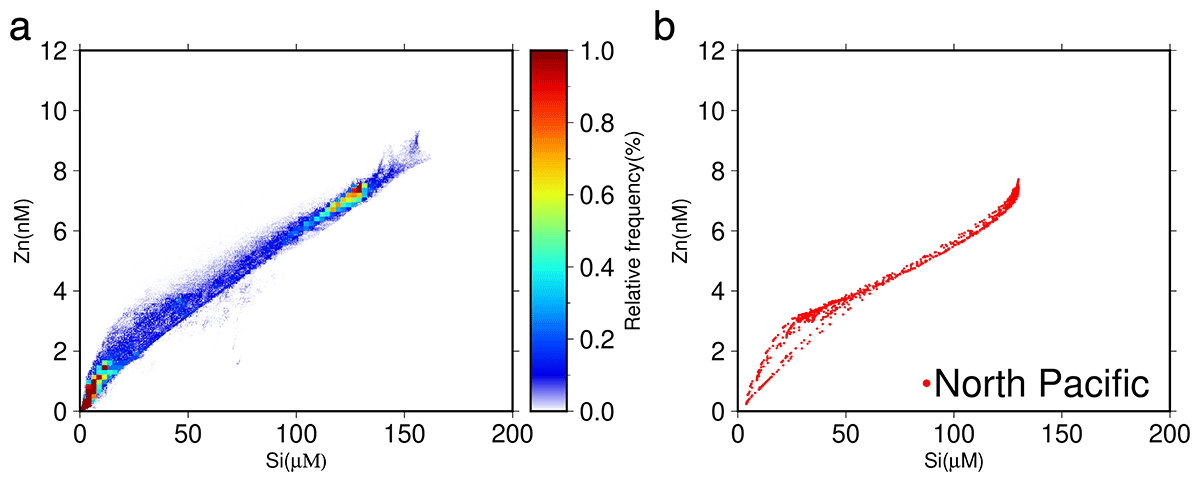
図2.北太平洋大陸棚における亜鉛供給を考慮しないモデル実験の珪素(横軸)と亜鉛(縦軸)をプロットした散布図
(a) 全球データの散布図。色付けはプロットデータの頻度を表す。(b) 北太平洋におけるデータ(GP02セクション; 図3(a)参照)の散布図。
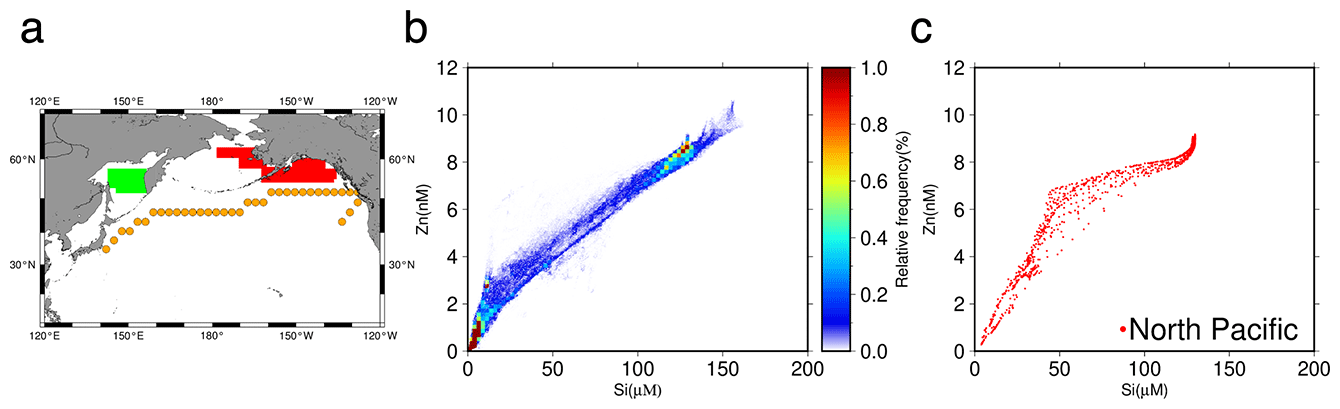
図3.北太平洋大陸棚における亜鉛供給を考慮したモデル実験の珪素(横軸)と亜鉛(縦軸)をプロットした散布図
(a) モデル内で設定された陸棚領域を示す。緑色がオホーツク海、赤色がベーリング海周辺海域として設定された場所である。オレンジの点はGEOTRACES GPO2セクションの観測点を示す。(B) 全休データの散布図。色付けはプロットデータの頻度を表す。(c) 北太平洋におけるデータ(GPO2セクション)の散布図。
社会的意義・今後の展開
本研究では、北太平洋大陸棚からの亜鉛供給が存在するならば、北太平洋における亜鉛分布が再現できることを示唆しています。しかし、オホーツク海およびベーリング海のいずれの大陸棚においても亜鉛濃度に関する詳細な観測データは少数であり、観測による大陸棚亜鉛供給の確実な証拠は得られていません。今後、北太平洋大陸棚近辺における亜鉛濃度がより詳細に観測されれば、大陸棚からの亜鉛供給の存在をより直接的に検証できることが期待されます。さらに陸棚からの溶出プロセス以外の仮説で観測事実を再現できる可能性についても検討を行うことが必要です。特に、北太平洋中深層における海洋循環については不確定性が大きく、その影響についてはより詳細に検証をしていく予定です。今後、亜鉛循環プロセスに着目した研究を進めることで、太平洋における海洋物質循環に関する新たな知見が得られることが期待されます。
なお、2024年9月18日に本論文にて日本海洋学会2024年度奨励論文賞を受賞しました。
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/aori_news/information/2024/20240918-2.html![]()
発表雑誌
雑誌名:Journal of Oceanography(2022年9月24日)79(1), (2023), 61–76
論文タイトル:Zinc and silicon biogeochemical decoupling in the North Pacific Ocean
著者:Kiminori Sugino*, Akira Oka*
DOI番号:10.1007/s10872-022-00663-4
アブストラクトURL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10872-022-00663-4![]()
用語解説
- (注1) 微量栄養塩元素
- 微量栄養塩元素とは、生物が生育や代謝に必要とする栄養素のうち、非常に微量で存在する元素のことを指します。これらの元素は、植物プランクトンの成長に不可欠で、代表的な元素には、鉄、亜鉛、銅、マンガンなどが含まれます。
- (注2) GEOTRACES計画
- GEOTRACES計画は、海洋中の微量元素やその同位体の分布と動態をグローバルな規模で調査する国際的な研究プロジェクトです。海洋における物質循環プロセスや微量元素の役割を理解することを目的としています。
問い合わせ先
杉野 公則(すぎの きみのり)
大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 博士課程
k-sugino◎aori.u-tokyo.ac.jp
岡 顕(おか あきら)
気候モデリング研究部門 准教授
akira◎aori.u-tokyo.ac.jp ※「◎」は「@」に変換してください
![]()
![]()

 教職員募集
教職員募集 所内専用
所内専用
