サンゴの身体のどこでどんな遺伝子が発現しているのか? ナガレハナサンゴのゲノム解読と組織別遺伝子発現解析
2024年10月24日

研究成果
発表者
新里 宙也 海洋生命科学部門 准教授
識名 信也 台湾海洋大学 教授
成果概要
サンゴは、地球上で最も生物多様性の高い「サンゴ礁生態系」を構成する重要な生物です。しかし、その生物学的知見は未だ不足しています。サンゴの1個体はポリプと呼ばれ、触手や口などの複数の組織から構成されています。ポリプを組織レベル、および細胞分子レベルで理解することは、サンゴという生物を正確に理解する第一歩です。東京大学大気海洋研究所の新里宙也准教授と台湾海洋大学の識名信也教授らの研究グループは、大型のポリプ(直径3-5cm)を持つナガレハナサンゴ(Fimbriaphyllia ancora)の全ゲノム全遺伝子情報、およびポリプを構成する各組織の細胞分子特性の一端を明らかにしました。本研究によりサンゴのどの部位でどのような生物学的反応が起こっているのかをより深く・正確に予測することができるようになりました。
発表内容
研究の背景
最も生物多様性豊かな海洋環境であるサンゴ礁、その礎となっているのが造礁サンゴです。造礁サンゴ(以下サンゴ)はイソギンチャクやクラゲなどと同じく刺胞動物の仲間です。多くのサンゴは単細胞藻類である褐虫藻と相利共生関係を築いており、褐虫藻から供給される膨大な光合成産物を栄養として利用しています。近年、地球温暖化によって海水温が上昇しており、サンゴと褐虫藻の共生関係の崩壊、白化現象が頻発しています。サンゴは栄養の大部分を褐虫藻に依存しているので、白化すると栄養不足に陥り、最悪の場合死に至ります。サンゴが死滅すると、そこを住処とする多様な海洋生物が生息場所を失い、生物多様性が喪失することが危惧されます。環境変動、特に地球温暖化の影響を受けやすいサンゴ礁を取り巻く状況は、日々厳しくなっています。サンゴの保護の必要性が増していく一方で、サンゴそのものの生物学的な知見はいまだ乏しいのが現状です。
研究内容
サンゴを拡大して観察すると、「ポリプ」と呼ばれるイソギンチャクのような個体が数多く集合している様子が見られます(図1)。多くの種類のサンゴはポリプが分裂してクローンを増やすことで成長し、1つの群体を形成します。サンゴの生活史の一例は、以下の記事でも紹介しています。
https://www.aori.u-tokyo.ac.jp/research/news/2023/20231018.html![]()

図1.サンゴのポリプの集合。個々のポリプの直径は1-2mmと小さい。
写真はハナヤサイサンゴ (Pocillopora damicornis) 。
ポリプはサンゴ群体を構成する最小単位です。ポリプを理解することは1つのサンゴ群体の理解のための第一歩であり、ひいてはサンゴ礁全体の生物学的解明に欠かせません。しかし多くのサンゴにおいて、ポリプの直径は1−2mmと小さいため、1つのポリプを単離し、さらにそれを構成する組織の特性を研究することは物理的に困難でありました。そこで台湾海洋大学の識名信也教授と東京大学大気海洋研究所の新里宙也准教授は、直径が3−5cmと大きなポリプを持つナガレハナサンゴ(Fimbriaphyllia ancora)に注目しました(図2)。ナガレハナサンゴは顕微鏡下で解剖が可能で、ポリプを構成する組織全てを単離することができます。

図2.本研究で使用したナガレハナサンゴ(Fimbriaphyllia ancora)。
個々のポリプの直径は3-5cm。他種のサンゴに比べて10倍以上大きい。
まずナガレハナサンゴの全ゲノム(注1)を解読し、約4億3千万塩基対のゲノム配列を決定しました。そこから約2万3千個の遺伝子(注2)を特定しました。ポリプを構成している4つの組織、触手、隔膜糸、体壁、口・咽頭を顕微鏡下で単理し(図3)、組織ごとに高いレベルで発現(注3)している遺伝子群を特定することで、それぞれの組織の役割を調べました。その結果、触手は防御や捕食、褐虫藻との共生やステロイド合成など、多様な役割を果たしていることが明らかになりました。隔膜糸は様々な消化酵素や光受容体が、体壁では免疫や骨格形成に関わる遺伝子が高く発現していました。口・咽頭では神経ペプチドや神経伝達物質の様々な受容体が高発現しており、サンゴの神経システムの重要な組織である可能性が示唆されました。
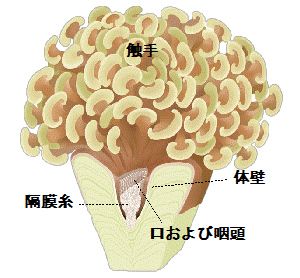
図3.ナガレハナサンゴ(Fimbriaphyllia ancora)のポリプの模式図、および各組織の名称
社会的意義・今後の展望
本研究により、サンゴポリプの各組織で機能している遺伝子群のリスト、まさにポリプを形成している「レシピ」とも言える詳細な情報が手に入りました。これまでのサンゴの遺伝子研究では、多数のポリプや組織が雑多に入り交ざった状態での解析を余儀なくされていたため、微小な生物学的反応が覆い隠され、重要な生物学的発見が見過ごされている状態でした。本研究で得られた全ゲノム情報や、組織ごとの遺伝子発現リストを統合することで、サンゴのどの組織でどのような生物学的反応が起こっているのかの予測が可能になり、より深く・正確にサンゴを生物学的に理解することができると期待されます。
東京大学大気海洋研究所と台湾海洋大学は国際交流協定を締結しており、本研究はその成果の一部です。台湾海洋大学のホームページでも、台湾初のサンゴゲノム解読の報告として本成果が紹介されています。
https://mprp.ntou.edu.tw/p/404-1017-102409.php![]()
発表雑誌
雑誌名:Communications Biology 7, Article number: 899 (2024)(2024年7月24日)
論文タイトル:Genome and tissue-specific transcriptomes of the large-polyp coral, Fimbriaphyllia (Euphyllia) ancora: a recipe for a coral polyp
著者:Shinya Shikina*, Yuki Yoshioka, Yi-Ling Chiu, Taiga Uchida, Emma Chen, Yin-Chu Cheng, Tzu-Chieh Lin, Yu-Ling Chu, Miyuki Kanda, Mayumi Kawamitsu, Manabu Fujie, Takeshi Takeuchi, Yuna Zayasu, Noriyuki Satoh, Chuya Shinzato*
DOI番号:10.1038/s42003-024-06544-4
アブストラクトURL:https://www.nature.com/articles/s42003-024-06544-4![]()
用語解説
- (注1)全ゲノム
- その生物が持つ全ての遺伝情報であり、生き物の命の設計図とも形容される。
- (注2)遺伝子
- 本稿では、タンパク質を合成する遺伝情報、mRNA(伝令RNA)を意味する。
- (注3)発現
- ゲノムDNAにコードされた遺伝情報がmRNAへと転写され、さらにタンパク質へと翻訳されて機能する過程。本研究における「遺伝子発現解析」は、遺伝子ごとのmRNAの量を意味している。
問い合わせ先:
新里 宙也(しんざと ちゅうや)
海洋生命科学部門 准教授
c.shinzato◎aori.u-tokyo.ac.jp
識名 信也(しきな しんや)
台湾海洋大学 教授
shikina◎mail.ntou.edu.tw (日本語可) ※「◎」は「@」に変換してください
![]()
![]()

 教職員募集
教職員募集 所内専用
所内専用
